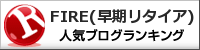(※このサイトはアフィリエイト広告を掲載しています)
今回は最近読んで面白かった本の紹介です。
タイトルは「資産防衛のためのダイヤモンド投資」(2022年、PHP)。
著者は15年にわたってダイヤモンドを取り扱ってきたという川端敬子さんという方。 いろんな意味で目からウロコの1冊でした。
消費用ダイヤと投資用ダイヤは別物
みなさんはダイヤモンドを投資対象として考えたことはありますか?
僕自身は全くありませんでした。
僕にとってダイヤモンドは、富裕層の奥さんが身に付ける贅沢品といったイメージ。
さらにいえば、知り合いの女性から「昔買ったダイヤのネックレスを買取査定に出したら二束三文のような値段を付けられた。ああ、腹が立つ……」というボヤキを聞かされたこともあります。
だから、これまでダイヤが資産防衛の手段になるとは思っていませんでした。
ところが、本書はこのような先入観をバッサリ切り捨てます。
曰く、消費用のダイヤモンドと投資用のダイヤモンドは全くの別物です、と。
消費用のダイヤというのは、デパートのジュエリーショップや街中の宝飾店で売られているような指輪やネックレスに加工されたダイヤのこと。
筆者によると、こうした宝飾品(ジュエリー)の値段というのは、台座の地金やデザイン料、さらに店舗運営費や広告費などが上乗せされているため、ダイヤそのものの原価とはかけ離れた金額に跳ね上がっているそうです。(なんか、新築マンションの話みたい)
だから、買値と同等の値段で売却するのはまず不可能。下手すると1/10くらいになってしまうこともあるとのこと。
なるほど、さきほどの知人女性などはまさにこのケースだったんですね……。
一方、投資用のダイヤというのは、原石をカットして磨いただけの裸石(ルース)を指します。
こちらは重量・色・透明度・カットの4要素からなる世界共通の品質評価基準があり、GIA(米国宝石学会)の鑑定で上位ランクの評価を受けた石は、国際相場で安定的に売買することができるそうです。
しかも、その値動きは、過去60年間ほぼ一貫して右肩上がり。インフレに強く、景気動向にあまり左右されないというのは確かに魅力だと感じます。
ちなみに、こうした投資用ダイヤを購入しようと思えば、最低でも50万円、できれば100万円以上の資金を用意しなければならないとのことです。
ポケットに収まる「有事の資産」
以上のような投資用ダイヤの特長を知ると、同じ実物資産で「有事の金」といわれる金(ゴールド)に似ていると感じます。
しかし、筆者の川端さんは金よりダイヤが優れている点として、その「携帯性」を強調します。
例えば2022年3月時点の相場で見ると、金1 グラム の価格が8000円程度なのに対し、ダイヤ1 グラム( =5カラット、ブリリアントカットなら直径11ミリくらい)の平均価格は3400万円以上。
もしも戦争や政情不安によって身ひとつで海外に脱出するような場合、金なら10キロ近くになるような額の財産でも、ダイヤならわずか数粒。これならポケットに入れて持ち運べる、というのです。
そして筆者は、第二次世界大戦中、ナチス・ドイツに強制連行されそうになったユダヤ人家族が、とっさに秘蔵していたダイヤモンドを飲みこんで隠すという「シンドラーのリスト」のワンシーンを紹介します。
実は、僕が本書の中で一番面白いと感じたのはこの部分です。
今の平和な日本では突飛すぎる想像かもしれませんが、世界史を振り返れば、人々が水と食料とわずかな貴重品だけ持って逃亡しなければならない事態というのは、結構な頻度で起きています。
いや、そこまでいかなくても、この日本でもほんの七十数年前、太平洋戦争直後のハイパーインフレに直面した政府が「預金封鎖」という手段を使って国民の預貯金を差し押さえ、「財産税」と称して国民の財産の大部分を没収するという悪夢のような出来事がありました。
かなり極端な仮定になってしまいますが、もしも将来、借金で国家破産の危機に陥った日本政府が同じような暴挙に出た場合、僕らが海外へ逃げようとしても銀行口座や証券口座が凍結されたら金融資産を持ち出すことは不可能です。
そういう事態まで想定して資産防衛を考えるなら、確かにダイヤモンド投資という選択肢は検討の余地があるような気がしてきます。
実際、本書によると、ユダヤ人や中華圏の人々の間では、富裕層に限らず、財産の一部をダイヤや貴金属に変えて手元に置いたり、そうした品を代々子孫に受け継がせたりする文化があるそうです。
というわけで、投資といえばインデックス投資と高配当株投資くらいしかやったことがない僕にとって、本書は未知の世界を垣間見せてくれた1冊でした。
実際にやるかと言われたら…
ただし。
本書を読んで今すぐダイヤモンド投資をやる気になったか問われれば、正直、今はまだそこまでの気持ちにはなっていません。実際に手を出すにはもっともっと勉強しなければ、というのが実感です。
例えば、ダイヤモンドのルースを取扱業者から購入する場合、石の原価にどのくらいの手数料を上乗せされるのか。
手数料は業者によって異なるのか、それとも統一されたルールがあるのか。
業者に提示された金額が妥当かどうか、購入する側が判断するにはどうすればいいのか。
将来ダイヤを売却したくなった時はどこへ持って行って、どんな手続きをすればいいのか。
その時はどのくらいの手数料を取られるのか。
そもそも日本で投資用ダイヤを扱っている業者はどのくらいいるのか、その中で信頼できる業者はどれなのか。
………
素人の僕には学ぶべきことが多すぎて、不動産投資と同じくハードルが高く感じられます。
しかしそれでも、混沌とした今の日本、今の世界を考えると、近い将来、ダイヤモンド投資を本気で検討しなければならない時代がやってくるんじゃないかという気がします。来るべきその日に備えて、今からこの本を熟読しておく価値は大いにあると思っています。