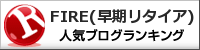今年もあと数日というこのタイミングで、年初に立てた「キンドル本を出版する」という目標をギリギリかなえることができました。
とは言っても、資産運用の本とか、FIREの本とかではありません。
「八つ墓村埋蔵金伝説~横溝正史最高傑作の謎を追う」というノンフィクション本です。
正直、かなりマニアックな内容なので、このブログの読者のみなさんに興味を持っていただけるかどうか、あまり自信はないのですが、せっかくなので今回は思いっきりこの本の宣伝をさせていただきます。
記者時代にやり残した謎解き
ご存じの通り、僕は大学を卒業してから45歳で早期リタイアするまでの20年余り、新聞記者をしていました。
新聞記者というのは通常、スペシャリスト(専門家)ではなくゼネラリスト(何でも屋)なので、担当する分野は様々なのですが、僕の場合は主に行政とか選挙とかの取材を任されることが多く、それにプラスして事件事故といった感じでした。
ただ、これは僕が自分から希望したことではありません。
実を言うと僕個人としては、こうした「社会性のある真面目なニュース」よりも、僻地に残る不可解な民間伝承とか、奇祭とか、未確認生物とか、そういうミステリアスなものを取材してみたいという願望を持っていました。
もちろん新聞ですから、オカルト雑誌のようにミステリアスなものをただミステリアスに取り上げるわけにはいきません。新聞らしく、きっちり事実関係を突き詰めながら、そういうミステリアスな話を論理的に読み解くような記事を書きたいという欲求を持っていたのです。
そして、本来の持ち場(行政・選挙・事件事故など)が比較的平穏なときは、実際にそういう案件に手を出して、新聞紙上に単発の記事を書いたり、連載をしたりといったことが何度かありました。それらの記事————自分の興味を追求した記事————を切り抜きしたスクラップ帳は今でも僕の宝物になっています。
ただ、「これは面白そうだ。よく調べて記事にしたい」と思いながら、時間や手間の制約から実現できなかった案件もたくさんあります。その一つが、今回出版したキンドル本のテーマである「八つ墓村埋蔵金伝説の謎」でした。
これはざっくり言うと、横溝正史の人気小説「八つ墓村」の中で描かれている戦国時代の埋蔵金伝説には、モデルとなった史実や伝説が存在するのか――――という謎です。詳しくは以下の紹介文をお読みください。
(※画像をクリックするとくっきり見えます。)
小説「八つ墓村」の舞台は、岡山県北部に設定された架空の村です。そして僕は今から十数年前、偶然にも記者として岡山県に赴任するという幸運に恵まれました。
これはもう、前々から興味を持っていた八つ墓村埋蔵金伝説のルーツ探しにチャレンジするしかない! 僕の胸はそんな野望で膨らんでいました。
しかし、現実はそう甘くありません。
当時は日々の仕事に追われ、自由な時間がなかなか取れなかったこともあって、ほとんど成果を出せないまま、僕は3年余りの岡山勤務を終えてしまいました。
で、それから10年ほど後、僕は新聞社を早期退職したわけですが、現役時代とは打って変わってヒマにあふれた生活を送るようなった結果、今度は「酔狂な一個人」としてこの謎に再挑戦してみようという思いが芽生えてきました。
この謎を調べたところで今さら新聞記事にできるわけじゃない。でも、とにかく自分の中で答えを出したい。どうせヒマなFIRE民なんだから時間はいくらでもかけられる。これこそ究極のヒマつぶしじゃないか――――というわけです。
(※ちなみに、僕は早期退職後、こんなふうに現役時代にやり残した謎解きに何件か挑戦しています。僕がFIRE生活の中で「ヒマを持て余して困る」という経験を一度もしたことがないのは、このあたりに理由があるのかも知れません。)
現地取材に訪れたとある山里で
こうして始めた十数年ぶりの再取材(?)ですが、いざやってみるとその作業が思いのほか面白く、予想以上にのめり込んでしまいました。
しかもそのうち、現地取材に訪れた中国地方のとある山村で、「これこそ八つ墓村伝説のモデルに違いない」と思えるような戦国時代の伝説や史跡を見つけ、そこに登場する400年前の人物の子孫を探し出して面談するという幸運にも恵まれました。
(※こうしたエピソードの一部はこのブログでも過去に紹介しています→こちら)
こうなってくるともう、「この取材結果を何らかの形で世間に発表したい」という欲求を抑えることができません。
そんなわけで取材が一段落した昨年の秋、「八つ墓村埋蔵金伝説の研究」と題してnoteに連載記事を書いてみたのですが、期待とは裏腹に読者の反響はまったくありませんでした。本当にまったく。僕としては「それなりに面白いものが書けたぞ」と思っていたので、これには相当がっくりきました。
まあ、ここで潔くあきらめていればよかったのかもしれませんが、往生際の悪い僕は「待て待て、こういう話はnoteよりも本にした方が読まれるんじゃないか。きっとそうだ。そうに違いない」と自分に都合よく解釈し、今年に入ってnote記事を全部削除。今度はキンドル出版を目指して追加取材を続け、原稿を加筆修正していきました。
そんなこんなで、このたびの出版にこぎつけたわけです。
とはいえ、最初にも書いた通り、かなりマニアックな内容なので、このブログを読んで下さっている方々にこの本を楽しんでもらえるかどうか、あまり自信はありません。どちらかというと、金田一耕助ファンとか、民俗学ファンとかの方々に向けて書いた本です。
「それでもヒマつぶしに読んでみるか」という寛大な方がいらっしゃれば、ぜひご笑覧下さい。レビューもお待ちしています。