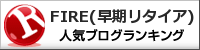(この記事にはアフィリエイト広告を掲載しています)
45歳で早期退職してから、早くも6度目の夏が巡ってきました。
僕にとってはFIREの喜びを最も感じる季節。
なぜなら、退職して以降、毎年夏は海辺の宿に滞在し、若い頃からの趣味である魚突きにどっぷり浸ることにしているからです。
たとえば去年(2024年)は、とある南の島で1カ月余りのプチ自給自足生活にチャレンジしました。(→詳しくはこちらの動画をご覧下さい)
2年前(2023年)は「日本最後の秘境」と呼ばれる鹿児島県トカラ列島の小宝島を訪問。(→詳しくはこちらの記事を)
3年前(2022年)は大ウツボを求めて伊豆諸島の式根島へ遠征してきました。(→詳しくはこちらの記事を)
もちろん、50歳となった今年も新たな旅に出かけます。
というわけで今回は、まもなく始まる2025年夏の魚突き旅行計画の紹介です。
今年は日本海・南の島の2本立て
まずは計画の全体像をお伝えしましょう。
今年は前半戦と後半戦の2本立てです。
前半戦は7月22日~8月8日、日本海側の某県にある自炊宿に17連泊。
後半戦は8月19日~8月29日、九州近海の島にある自炊宿に10連泊。
あわせて27泊となります。
去年のように1カ所で1カ月暮らすという選択肢もあったのですが、今回は少し趣向を変えて、ひと夏で生物相の違う2つの海を味わってみることにしました。
なお、前半戦と後半戦の間(世間が観光客でごった返すお盆の時期)は、自宅でゆっくり休養を取ることにします。
それでは、前半戦から詳しく内容を説明していきましょう。
滞在先の譲れない条件
なぜ前半戦の舞台に日本海を選んだかというと、僕はここ数年、伊豆諸島やトカラ列島といった南の海にばかり出かけていたからです。
これらの海域はとにかく水が温かく、サンゴ礁が綺麗で、泳いでいて気持ちいい。
ただ、そういう海で南方系の魚ばかり捕まえて食べていると、だんだん飽きてくる。
瀬戸内地方出身の僕としては、やはりカサゴ、カワハギ、ウマヅラハギといった馴染み深い魚の味が恋しくなってくるわけです。
とはいえ、多くの都市に囲まれた瀬戸内海は正直言って水質がいまいち。海に潜っても透明度が低いので魚突きには向いていません。
では、カサゴやカワハギがたくさんいて、しかも水質の良い海はどこかといえば、それはやはり日本海です。
というわけで、今年の春先から暇を見つけてはインターネットで日本海沿岸の滞在候補地を探してきました。
僕の重視する条件は以下の通り。
・魚突きが認められた海域である。(県によっては禁止されている)
・大都市から離れている。(都市部の海は水質が悪い)
・護岸整備されていない岩場が多い。(砂浜より岩場の方が魚が多い)
・自炊可能な安宿がある。(捕獲した魚で自給自足できる)
・宿と海が近い。(徒歩で行き来できるのがベスト)
率直に言って、これらの条件にピッタリ当てはまる滞在先を見つけるのは結構大変です。
そもそも日本の宿泊施設って、ホテルであれ旅館であれ民宿であれ、出来上がった食事を客に提供するところがほとんど。宿泊者自身が備え付けのコンロや炊飯器を使って自炊できるタイプの宿はそれほど多くありません。
でも僕の場合、旅先で自分が獲った魚を食べるという行為自体が目的なので、自炊可能というのは譲れない条件なのです。
しかし、運良くそういう宿を見つけても、海から離れた街中にあることがほとんど。これでは気軽に魚を獲りに行けません。
また、海岸近くにそういう宿があったとしても、Google地図の航空写真で付近の海岸線を確認したら砂浜と防波堤ばかりで岩場が全然ない、という残念なケースもあります。
というわけで、Google地図を眺めながら延々と候補地を物色するわけですが、今年もこの儀式を何日間も繰り返した末、ようやく納得できる滞在先を見つけることができました。
諸般の事情により具体的な場所は伏せますが、ご参考までに宿の周囲の海岸の一部をお見せしましょう。
どうですか、このいかにも魚がたくさんいそうなゴツゴツした荒磯!
さっそく宿に電話して17連泊の予約を入れました。
(※こういう田舎の宿はオンライン予約に対応していないことも多いです)
食材をどう確保するか
さて、こういう自炊宿に長期滞在する場合、重要なのは日々の食材の確保です。
僕の魚突き旅行は動物性タンパク質を自前で調達することを目標としているので、メインのおかずは海に潜ってヤスで突いてきます(もしくは釣ります)。
したがって、豊漁ならばその日の食卓は豪華に、不漁ならば食卓は貧相に。この出来高制が旅をスリリングなものにしてくれます。
一方、お米や野菜はさすがに自給できないので、地元のスーパーで買うことにしています。
ところが、今回泊まる宿はかなり辺ぴな漁村に立地しているので、Google地図で周辺をリサーチしても目立った店は見当たりません。
これがもしマイカー旅行なら必要に応じて近隣の町へ買い出しに行けばいいのですが、あいにく今の僕にはマイカーがない。買い出しするならバスを使うことになりそうですが、毎日そんなことをしていたら海に潜る時間がどんどん削られてしまいます。
というわけで今回の旅行では、魚以外の食材をある程度事前に準備しておくことにしました。
まずは主食の米。
滞在中の健康管理のためにもなるべくいろんな栄養を取りたいので、白米に胚芽押麦や粟・きび・大豆・小豆などを混ぜた雑穀米を数キロ持参します。
それから乾燥野菜。
こちらはトマト・ズッキーニ・ナス・アボカド・ブナシメジ・舞茸を天日干しで軽量化し、袋に詰めて持っていきます。
本当はもっとたくさん作るつもりだったんですが、出発前に雨が続いたせいであまり用意できませんでした。
恐らくこれだけじゃすぐになくなってしまうだろうから、滞在中に何度か買い出しに出かけざるを得ないと思います。
このほか、醤油・味噌・粉わさび・乾燥ワカメなども少量ずつ用意しました。
なお、こういうプチ自給自足旅行は、食材以外にもシュノーケルセット、魚突き用のヤス、釣り道具、クーラーボックス、着替えといった具合に荷物が多くなるので、今回は一切合切を段ボール箱に詰め、宅配便で宿へ送ることにしています。
ここまで読んで「ずいぶんと手間のかかる旅行だな」とあきれた方がいるかもしれませんが、人生であと何回やれるかわからない魚突き旅行を心おきなく楽しむためには、このくらいの手間は厭いません。
むしろ、旅行中に起こる様々な事態をシミュレーションして準備を整え、かつ、知恵を絞って荷物を軽量化する作業は楽しいものです。
今年の新兵器、カメラ固定型マスク
さて、今回の旅行で初めて導入する新兵器をご紹介しておきましょう。
それはカメラ固定型の水中マスクです。
以前の記事でも書きましたが、僕は昨年の南の島旅行に合わせて水中撮影に適した米国製の「ゴープロ」というカメラを購入し、その魅力にとりつかれました。
ただ、海の中で片方の手でゴープロを構えていると、なかなか自由自在に泳ぐことができません。
そこでゴープロを頭の前に固定して、両手が空いた状態で撮影できるよう、この水中マスクを購入したわけです。
ちなみに値段は2480円。思っていたより安く済みました。
果たして、頭に固定したカメラを手探りでうまく操作できるのか?
…という不安は残りますが、ぜひとも昨年を上回る素晴らしい海中動画をものにして、YouTubeで配信したいと意気込んでおります。
後半戦は一棟貸しの宿
それでは次に後半戦について。
こちらも具体的な場所は伏せますが、僕が去年の夏に1カ月滞在した島とはまた別の九州近海の南の島になります。
観光地としてはほぼ無名であり、僕にとっても未踏の土地ですが、書籍やブログでこの島を訪れた人の体験談などを読むと、大自然が残っている島だということが伝わってきます。
この島で僕が泊まる宿は、一棟貸しの宿。
僕のような1人旅にはもったいない物件なのですが、ともに旅するパートナーがいないので仕方ありません。
(ちなみに、うちの妻は僕が魚突き旅行に行こうと誘っても「そんなしんどい旅はしたくない」と言って同行してくれません。子供たちもすでに高校生以上なので親同伴の旅行には行きたがりません。学生時代の友人や元同僚はみんな忙しく働いていて、僕の旅行に付き合ってくれる人は誰もいません。)
まあ、一棟貸しとは言っても、そこは観光地化されていない島なので、料金はたかがしれています。なんと1泊5000円。この値段でキッチンも風呂もトイレもあって、調理器具も一通りそろっている海の真ん前の一戸建てを独占できるのだから、むしろ破格と言っていいくらいでしょう。
それでは7月22日から、灼熱の都会を離れて魚突き三昧の日々を送ってきます。
まずは日本海へ、そして南の島へ。
旅先の様子は例によってX(旧Twitter)で順次報告していきますので、そちらもぜひご覧下さい(僕のXアカウントはこちら)。
〈追伸〉