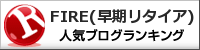目標は「所得税0・住民税0・国保料7割減」
今回は、早期リタイア後の家計を楽にするために、強制的に徴収される税金や社会保険料の負担を極限まで小さくする方法について考えてみたいと思います。目標は「所得税ゼロ・住民税ゼロ・国民健康保険料7割免除」の三冠達成です。
さて、みなさんは自分が毎年納めている税金や社会保険料が大体どれくらいの金額か知っていますか。恐らくほとんどの方が把握していないと思います。
サラリーマンだったころの僕もそうでした。というより、今でも当時どのくらい納めていたのかよく知りません。
そこで物置の奥から現役時代の源泉徴収票を引っ張り出してきました。退職直前の2019年のものです。
所得税、住民税、社会保険料と足していくと……なんと合計数百万円! 現役時代はこんなに重い負担を背負っていたのか、と今更ながら驚かされます。
しかし、早期リタイアすれば、こんな重税とはオサラバできます。
収入がなくなるかわりに負担もほとんどなくなってしまう。それが全く働かないフルリタイアのいいところでしょう。
ただ、株式の配当金やETFの分配金で生活費を賄っている場合は、多少の税負担が生じる可能性があります。
では、このような配当収入を年間いくらまでに抑えれば、負担を最小化できるのか。すなわち、「所得税ゼロ・住民税ゼロ・国民健康保険料7割免除」の三冠を達成できるのか。これから検証してみようと思います。
なお、これから紹介するシミュレーションは全て2022年12月時点のデータに基づいて行っています。また、話を簡単にするために、アルバイトや不動産賃貸業など配当以外の収入はないという前提で話を進めます。
配当48万円以下なら所得税ゼロ
まずは国に納める所得税です。国税庁のHPによると、所得税には48万円の基礎控除があります。ですから、年間に受け取る配当金・分配金が48万円以下であれば、所得税は無条件で非課税となります。
具体的にいうと、証券会社の特定口座にある国内株式の配当金から源泉徴収された所得税も、米国ETFの分配金から源泉徴収された所得税も、きちんと確定申告をすれば全て還付金となって戻ってくるわけです。
もちろん、年間の配当収入が48万円を多少超えても、国内株式の配当金であれば配当控除を使って所得税をゼロにすることはできます。ただ、米国ETFの場合は、外国税額控除を使っても控除限度額が設定されているので全て取り戻すのは困難です。所得税を完全にゼロにしたいと考えるなら、この48万円のラインを覚えておいた方がいいでしょう。
なお、所得税には基礎控除のほかに扶養控除などもあるので、家族構成などによって非課税条件が緩くなりますが、話が複雑になるのでここでは省略します。
配当45万円以下なら住民税ゼロ
次に住民税を見てみましょう。こちらは自治体が徴収する税金なので国の基準があるわけではありません。そこでとりあえず、横浜市の例で考えてみることにします。
横浜市のHPによると、住民税が非課税になるのは前年の所得が45万円以下だった場合です。つまり、1年間に受け取る配当金・分配金を45万円以下に抑えれば、翌年の住民税は無条件でゼロになります。所得税と比べると3万円だけ条件が厳しいわけです。ただし、こちらも所得税と同じく家族構成によっては非課税となる条件が緩くなります。
なお、参考までに大阪市、名古屋市、福岡市の制度も調べてみましたが、無条件で住民税非課税となるラインは、いずれも横浜市と同じく「45万円以下」でした。お住いの街の状況を知りたい方は「〇〇市 住民税 非課税」と検索してみてください。
配当43万円以下なら国保料7割免除
最後は国民健康保険料です。
残念ながら、これだけは配当収入をいくら抑えてもゼロになりません。なぜなら、国民健康保険料には、収入に応じて課せられる部分(所得割)と、収入に関係なく同じ額が課せられる部分(均等割)があり、均等割は基本的になくならないからです。
ただし、収入(より正確に言えば、世帯全体の前年の所得)が一定額を下回れば、この均等割も2割免除、5割免除……と段階的に軽減されます。なので、最も負担が軽くなる7割免除の条件を見ていくことにしましょう。再び横浜市の例を参考にします。
横浜市のHPによると、7割免除の条件は43万円以下。住民税よりさらに厳しい条件です。(ただし、世帯の中に年金受給者がいるような場合は条件が多少緩くなります。)
では仮に、早期リタイアした45歳の独身者で配当収入がピッタリ43万円だった場合、保険料はいくらになるのでしょうか。計算式は結構ややこしいので結論だけ言います。1年間の保険料は均等割7割免除の適用を受けて1万8210円となります。
じゃあもし、この人の配当収入が43万1円だったら保険料はどうなるかといえば、3万350円です。配当収入が1円増えただけで7割免除が5割免除になってしまい、保険料が1万円以上高くなってしまうのです。
この「1円の差」を甘く見てはいけません。国民健康保険料というのは被保険者の数、つまりその世帯の家族の数が多くなるほど高くなってゆきますから、大家族ほど影響が大きくなります。
例えば、夫婦と小中学生の子どもが3人いる世帯の場合、配当収入がピッタリ43万円なら保険料は7万7560円ですが、配当収入が43万1円になったら保険料は12万9280円に跳ね上がります。その差は5万円以上です。
なお、こちらも大阪市、名古屋市、福岡市の制度を調べてみました。無条件で国民健康保険料の均等割が7割免除となるラインは、やはりどこも横浜市と同じく「43万円以下」でした。お住いの街の制度を知りたい方は「〇〇市 国民健康保険料 減免 7割」と検索してみてください。
三冠を狙うならインデックス投資
以上のことから、「税や社会保険料の負担軽減にとことんこだわるなら、早期リタイア後の配当収入は年間43万円以下に抑えるべし」というのが僕の結論となります。このラインさえ守れば上記の三冠が達成できるわけです。
(ついでに言うと、国民年金保険料の全額免除を申請して四冠を達成することも可能です。ただ、これについては将来のデメリットも考えて慎重に判断すべきだと考えています。詳しくはこちらの記事で。)
しかし、この三冠を達成しようと思えば、当然のことながら、FIREの王道の一つである「高配当株投資のインカムゲインで生活費を全て賄う」という生活スタイルは選択できなくなります。
では、どうすればいいのでしょうか。
実は、僕が早期リタイア後の資産運用方針として、高配当株投資ではなくインデックス投資を選んだ理由の一つがここにあります。インデックス投資なら、課税対象となる所得を発生させずに、資産を成長させることができるからです。
(僕の資産運用の基本方針はこちらの記事に詳しく書いています。)
例えば僕はこういう方法を実践しています。
自分の資産を銀行預金とインデックスファンドに半々くらいの比率で配分して、日々の生活費はひたすら銀行預金から取り崩す。これならインデックスファンドが値上がりしても含み益が生じるだけで、売却しない限り所得は発生しません。
今のところ、今後5年間くらいはこの方針でやっていこうと思っています。そのうち、銀行預金(無リスク資産)の比率が減って、インデックスファンド(リスク資産)の比率が上がってきますから、その時点で自分のリスク許容度と相談しながらインデックスファンドの一部を現金化するかどうか検討するつもりです。
最後に一つ補足しておくと、僕は高配当株投資も魅力的な投資法だと思っているので、配当金が年間43万円のラインを超えない範囲で楽しもうと考えています。配当利回りを4%と仮定すれば、高配当株に1000万円投資しても年間の配当金はこの枠に収まりますからね。
おすすめ記事:新NISAの成長投資枠で何を買うべきか